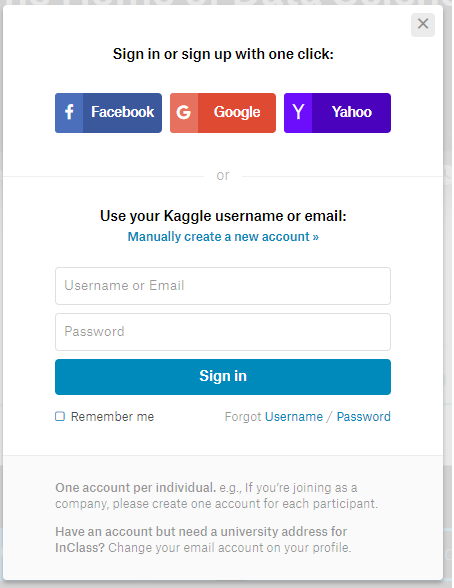数年前、ロッキード・マーティン社が、10年以内に小型核融合炉を実用化すると発表したニュースを覚えている人は居るだろうか。当時も、核融合研究の将来性と未来のエネルギー供給に対する、なんとなしの楽観論が広がっていたように思う。どうやら、核融合には私たちの心を捉えて離さない「何か」があるらしい。
本書『Sun in a Bottle』は、副題にも表されている通り、核融合研究の失敗史を通して、その「何か」--希望的観測 (wishful thinking) -- が、どんなふうに表れるのかに迫った本だ。
***
著者チャールズ・サイフェは、数学とジャーナリズムの修士号を持つ著名科学ライター。日本語には、『異端の数ゼロ』、『宇宙を復号する』といった本が翻訳されている。後述する通り、Science誌のニュース記者として働いていた経歴があり、核融合に関する科学スキャンダルにも若干の縁がある人だ。
***
核分裂と核融合について、簡単にまとめておく。(2章、1章)
核分裂と核融合も、根底にある原理は同じものだ。物理学に詳しくない人でも、アインシュタインの等式  を一度は眼にしたことがあるのではないかと思う。この式は、(原理的には) 質量m が、光速cの二乗を掛けた膨大な量のエネルギーE へと変換できることを述べている。核分裂の場合は、ウランやプルトニウムのような重く不安定な原子核が分かれる時、核融合の場合は、(重)水素のような軽い物質の核がくっつく際に、わずかながら質量が失なわれる。その失われた質量が、熱などの形でエネルギーに変わる。太陽や夜空の星が輝くのも、その内部で核融合が起こっているからだ。
を一度は眼にしたことがあるのではないかと思う。この式は、(原理的には) 質量m が、光速cの二乗を掛けた膨大な量のエネルギーE へと変換できることを述べている。核分裂の場合は、ウランやプルトニウムのような重く不安定な原子核が分かれる時、核融合の場合は、(重)水素のような軽い物質の核がくっつく際に、わずかながら質量が失なわれる。その失われた質量が、熱などの形でエネルギーに変わる。太陽や夜空の星が輝くのも、その内部で核融合が起こっているからだ。
核物理学の物理理論は1930〜1940年代ごろまでにほぼ発見され、商用核分裂炉の実用化とほぼ時を同じくして核融合炉の研究開発も始まった。1952年には、アメリカの水素爆弾実験アイヴィー・マイクによって、核融合を人工的にも発生させられることが証明された。以来60年以上にわたって、核融合反応から持続的にエネルギーを取り出す方法の開発が進められている。
しかし、核分裂炉は、もともと不安定な物質を使うため、(核融合と比較すれば)容易に実現できる(それゆえに暴走の危険もある)のに対して、核融合炉は普通の環境では自然には進まない反応を利用するため、反応を発生させ持続させることは非常に困難であることが分かったのだ。
***
本書は、核融合炉研究が始まる少し前、原子爆弾(核分裂の爆弾)および水素爆弾(核融合爆弾)の研究開発から語られる。核融合研究の科学的・工学的側面の説明と共に、研究者たちの人間模様にも光が当てられている。ややドラマチックすぎるようにも感じるものの、小説のように面白く読めた。(核物理学の専門用語を除けば、英語の文章も明快で非常に読み易いと思う)
優秀な物理学者でありプロジェクトマネージャであったものの、身内に多くの共産党員が居たためにソ連のスパイではないかと疑われた「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーと、共産党政権下のハンガリーからアメリカへと亡命し、それゆえに強硬な反共・反ソ派である「水爆の父」エドワード・テラーの確執と対立。(1章) オッペンハイマーは反原子力運動にかかわり、核物理学の研究から追放されることになる。その後、テラーは水爆を開発し、土木工事のために水爆を用いる "plowshare" 計画を進めるものの、放射能汚染の問題を解決できず、結局計画は放棄されてしまう。(3章) テラーは、変人的なまでの楽天主義者であったという。同僚科学者は、楽観の度合いを表して「1テラー」という単位を使っていたそうだ。
核融合炉研究における不正と錯誤の歴史は、研究自体の歴史と同じ程度に古い。さしたる物理学上の業績もないまま、アルゼンチンのフアン・ペロン大統領に取り入り、全世界に「人類初の制御核融合実現」を宣伝した元ナチスの科学者ロナルド・リヒター。やはり世界中に成功を宣伝したものの、結果的に実験装置の不備による誤検出であったと判明した、英米の共同研究プロジェクトであるZETAプロジェクト。(4章)
それでも、1950年代〜1960年代ごろまでにはアメリカで、その後世界各地でも、短時間の制御された核融合反応が実現した。ただし、そのためには外部から大量のエネルギーを投入しなければならず、対して発生したエネルギーはごく僅かなものではあった。
***
核融合反応を起こすためには、互いに反発し合う原子核同士を、極めて近い距離まで接近させる必要がある。そのためには、燃料となる重水素を、超高温かつ超高圧に保たなければならない。水素爆弾の場合は原爆の熱エネルギーが、恒星の場合は巨大な重力がそのエネルギーを供給している。
数十年以上にわたって、「超高温かつ超高圧」を実現するための方式として、2種類の方法が研究されてきた。電磁力を用いて重水素のプラズマを狭い範囲に圧縮する「磁気閉じ込め方式」、もう1つはレーザー光線の照射で燃料を圧縮する「慣性閉じ込め方式」だ。しかし、研究が進められるにつれて、磁気閉じ込め方式も慣性閉じ込め方式も、小規模の装置では核融合反応を実現できないと判明した。装置の規模は巨大化し、その建設費用も1国の予算では到底賄えない規模にまで膨れ上がっていった。(5章)
常温核融合という「科学史上最大のスキャンダル」が発生したのは、核融合の新たな原理が求められていた、ちょうどそんな時代であった。
***
1989年に発生した常温核融合の騒動 (6章) にはかなりの紙面が割かれている。「常温核融合」を「発見」したのは、アメリカ、ユタ大学のポンズ教授とイギリス、サウサンプトン大学のフライシュマン教授だ。彼らは、核物理学を専門とする物理学者ではなく、化学者であった。核融合炉の実験炉の建設費用は数十億ドル、数百億ドル単位にも達しようかという時期、2人の研究者の主張によれば、ビーカーに入れた重水にパラジウムの電極を使って電気を流すだけで核融合反応が発生するのだという。
おそらく、2人の教授が観察した現象は、最初はちょっとした思い込みと実験条件の不備だったのだろう。(当時アメリカで行なわれていた核実験から生じた放射性降下物の混入を、核融合の生成物と取り違えたのではないかと言われている) 次第に、新たな発見がメディアから注目され、州・連邦政府から補助金が支出される計画が立てられるに従い2人は後に引けなくなり、実験結果の改竄にまで手を染め、科学会から追放されアメリカを去るハメになってしまう。
常温核融合スキャンダルの展開は、まるで研究不正のテンプレートのように見える。科学論文の発表よりも、一般メディアのプレスリリースを通して大々的に世間の注目を集めたこと。当初は、他の科学者からも「追試に成功した」という報告があったこと(その後ほとんど取り下げられた)。次第にネガティブな結果が増えていっても、当の本人たちは決して自身の誤りや不正を認めなかったこと。最後は、科学的な議論よりは社会的・政治的なレベルで決着を付けるしかなかったこと。これは近年の研究不正の騒ぎとも酷似している。
ちなみに、発表当初から2人の教授を擁護したブリガムヤング大学のスティーブン・ジョーンズ教授は敬虔なモルモン教徒でもあり、その後「ナザレのイエスは、実は中央アメリカを訪れていた」ことを証明しようと試みる研究に入り込んでいったというオマケが付いている。
その後も、1990年代のバブル核融合 (7章) において、常温核融合の悲喜劇は繰り返されることになる。潜水艦モノの映画が好きな人であれば、スクリューから生じる「キャビテーションノイズ」という言葉を聞いたことがあるかもしれない。単純に言えば、船のスクリューなどにより液体が高速で動かされると、液体の内部に「キャビテーション」という(真空の)小さな泡が生成される。ここで観察されたバブル核融合は、重水素を含む液体 (アセトン) に超音波を当てた際に生じるキャビテーション内で生じるとされた。泡が潰れる時にその内部は高温高圧になるため、そこで核融合反応が起きることが「観測」されたという主張がされたのである。付け加えておくと、キャビテーション内部の温度と圧力は、核融合が起こると考えられていた条件よりも数桁低く、発見者のグループ以外の研究者は誰も追試に成功していない。
バブル核融合の論文がScience誌に受理されたとき、サイフェ氏はScience誌のニュース編集部 (査読論文の編集部とは別部門) に勤務しており、一連の騒ぎを "ground zero" で目撃することになった。かなり早い段階から、彼は論文著者や査読者とコンタクトを取り、独自の取材と考察を深めていった。論文誌の査読プロセスの自律性を守ろうとするScience誌の編集長と、常温核融合の二の舞を防ぎたい核物理学コミュニティ(特に、論文著者の所属機関であるオークリッジ研究所) の間の綱引きへと、否応なしに著者は巻き込まれていく… バブル核融合の顛末は、著者が騒動に近い場所にいたこともあり、非常に臨場感があって面白かった。
***
主流派の核物理学者たちも、大して好成績を挙げているとは言い難い。1985年に米ソ間の合意から始まった国際的な核融合炉研究プロジェクト「ITER」は、各国の政治的な思惑から遅れに遅れ続け、建設地を決めるのでさえ20年近く要するありさまだ。当初計画では2018年には稼動開始の予定であったものの、現在でも更に遅れが続いている。
私も明確には知らなかったのだけど、これら現在実際に進行中のプロジェクトは、あくまで「核融合とプラズマ」に対象を絞った一種の学術研究であり、「実用的な発電所」の実現を目指したエンジニアリングではないのだという。持続的に核融合反応を継続させることは、おそらく可能ではある。それでも、発生したエネルギー (中性子) を吸収して、熱を発生させて、利用可能な形でエネルギーを取り出す方法の開発は、こういった「核融合炉」プロジェクトの対象外である。たとえて言うならば、「薪木」に点火して燃やし続ける方法はようやく分かってきたものの、火にくべて湯を沸かすための「ヤカン」の作成方法を理解するには、まったく別の研究を進めなければならない。だから、今のところヤカンの耐久性、運用方法や処分方法もよく分かっていないというのだ。
核融合の研究においては、ほぼ60年の全史を通して、あまりに度が過ぎた楽観主義と錯誤、最悪の場合は研究不正が繰り返し繰り返し起こってきたことが、豊富な事例をもとに示されていた。
***
最終章 (10章) では、科学研究の推進力であり不正と失敗の温床でもある「希望的観測」についての考察が取り上げられている。
テクノロジーの開発は、「かつて不可能だったこと」を可能にするものだ。これまで不可能だった領域に、前人未踏の領域に踏み込み、かつて誰も成し遂げたことのない新たなテクノロジーを開発するためには、何らかのビジョン --「世界をこう変えたい」という希望と信念-- が必要とされる。--「無尽蔵のエネルギー」、「人間レベルの知能」、「不老長寿」など。こういったビジョンは、科学者が直接的に言及することは少なくても、科学研究を裏付ける原動力なのだ。テクノロジーには、希望的観測を実現していく力があることは否定できない。
ところが、この「希望的観測」が暴走したり悪用されたりした場合、存在しない現象を観察・捏造してしまったり、既に間違いが示された結論を延々と擁護し続ける状況に陥ってしまう。最後は、社会がそのビジョンを是認するか否かという、科学的な根拠と論理とは別レベルでの決着となることがある。この種の社会的レベルでの決着は、たいていの場合、科学コミュニティそのものを傷つけ、更には「自身の権威や利権が脅かされることを恐れた守旧派科学者の圧力だ!」という陰謀論を産み出し、いっそう深く永続的な傷をもたらす場合すらある。
科学とテクノロジーは、希望的観測に対する解毒剤となる一方で、希望的観測そのものとなってしまう場合もあるらしい。では、一体科学におけるビジョンと希望的観測をどう扱えば良いのだろうかという問題に、本書は明確な解答を示していない。おそらく、誰も解答を与えることはできないだろうと思う。それでも、我々が自身の思考パターンから逃れられないのならば、せめてそのパターンの存在を知っておく必要があるのだろう。
***
本書は少し古いため、近年の状況には追い付けていない部分もある。たとえば、著者は核融合炉の研究よりは既に実用化された核分裂炉の利用を推進するべきだと述べているものの、福島第一原発の事故を見た後では安直に原発を推進する気にはなれないのではないだろうか。
それでも、ITER計画は遅延と予算超過が延々と続き、常温核融合の子孫を奉じるフリンジ的な科学者グループが論文ではなくプレスリリースを公表している状況を見る限りでは、本書で書かれた状況はそれほど変化していないのではないかと思う。核融合を専門とする研究者が語りたがらない失敗史、そして科学研究の裏にひそむ「希望的観測」の分析として、稀有で有用な本だった。
なお、最初に取り上げたロッキード・マーティン社の小型核融合炉は、その後ひっそりと、当初の設計サイズの100倍に巨大化する可能性があるという報道がされている*1。おそらく、この小型核融合炉も「希望的観測」の新たなページを刻み、その後世間から忘却されることになるのだろう。
The real danger of wishful thinking comes not from the individuals but from the wishful thinking at the very core of the science, is what makes the dream of fusion energy so dangerous to science. (p.225)
希望的観測の本当の危険は、個人からではなく科学の最央部にある希望的観測から生じる。これが、核融合エネルギーの夢を科学に対して極めて危険なものとしている。